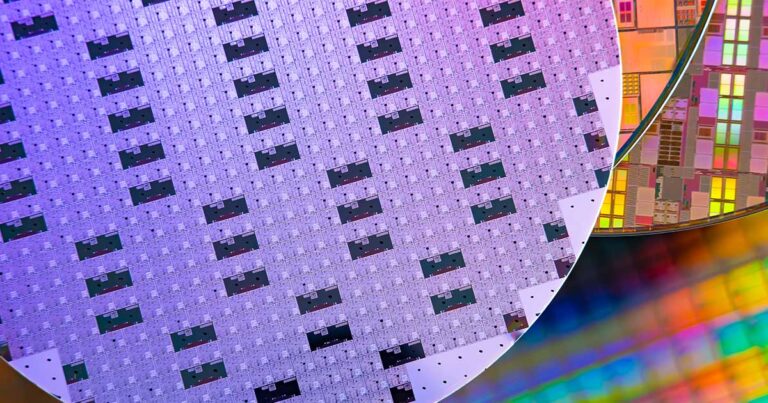この記事のポイント
- 一般NISAとつみたて(積立)NISAの共通点は「非課税である」ことだけ
- 非課税投資期間、非課税投資枠、投資方法に違いがある
- 少額から始めて超長期(10年以上)で運用したいなら「つみたて(積立)NISA」
- 投資経験者で、まとまった大きな資金を活かすなら「一般NISA」
- 20代からNISAを始めれば、最大限の恩恵が受けられる
「一般NISAとつみたて(積立)NISAの違いは何?」
「少額から始めたい私に向いているNISAはどっち?」
通常は、投資商品を購入するための特定口座をつくり、運用益が出た場合には税金が課されます。
しかし、NISA口座で購入した投資商品から運用益が出た場合は、ある一定期間は非課税です。
NISA制度は、一般NISAとつみたて(積立)NISAに制度がわかれていますが、はじめて存在を知った方にはそれらの制度の違いがわかりにくく、迷ってしまうことでしょう。
そこでこの記事では、2つの制度の違いや、どちらの制度があなたに向いているかが分かるように解説しています。また、NISAを始めるためには、NISA口座の開設が必要なため、投資初心者におすすめの証券会社も紹介しています。
この記事でおすすめしている証券会社では、口座維持費はかからないため、取り急ぎ口座開設だけでも大丈夫です。
※この記事は2024年5月時点の情報をもとに作成しています。
目次 ー Contents
- NISAとは
- 一般NISA・つみたて(積立)NISAの違いは
- 一般NISAのメリット・デメリット
- つみたて(積立)NISAのメリット・デメリット
- 【一般NISAがおすすめな人】大きな資金があり自分の考えで投資をしたい人
- 【つみたて(積立)NISAがおすすめな人】少額から始めて長期で運用したい人
- 投資初心者はどちらのNISAを選ぶべき?
- 【年代別比較】一般NISAとつみたて(積立)NISAのどちらがお得?
- 一般NISA・つみたて(積立)NISAの併用はできないが切り替えは可能
- 一般NISAとつみたて(積立)NISAの併用が2024年の新制度により可能になる
- 【比較】おすすめネット証券会社5選
- 一般NISAとつみたて(積立)NISAおすすめ銘柄商品5選
- 一般NISA・つみたて(積立)NISAの違いに関するよくある質問
- 【まとめ】一般NISA・つみたて(積立)NISAの違いまとめ
NISAとは
NISAとは、あなたが金融商品を購入する際に利用できる、特別な口座の1つです。
NISA口座で購入した金融商品から得られた利益については、年間の上限金額内なら税金が課されない──。NISAにはそのような特長があります。
一般的な投資口座では、利益部分に対して20.315%の税金が発生するため、このNISA制度は、非常に魅力的な制度となっています。
たとえば、年間の投資枠の範囲内で購入した金融商品に限りますが、その金融商品から得られた収益は全額非課税になります。
つまり、あなたが投資から得た利益すべてを、税金を気にすることなく手元に残せるということを意味するのです。
この制度を利用するためには、金融機関でNISA口座を開設し、その口座を通じて投資を行う必要があります。
この制度を理解し、うまく利用することで、あなたの投資生活はより有利に、そして資産形成はよりスムーズに進められるでしょう。
一般NISA・つみたて(積立)NISAの違いは
| 一般NISA | つみたて(積立)NISA | |
|---|---|---|
| 非課税投資期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
| 非課税投資枠 | 年間上限120万円 (5年間で計600万円) | 年間上限40万円 (20年間で計800万円) |
| 投資方法 | ・積立方式 ・スポット購入 | ・積立方式 |
| 投資対象商品 | 個別株式 ・投資信託 ・ETFなど | 金融庁に届け出された投資信託233本 (2023年6月23日時点) |
NISA制度には大きく分けて2つのタイプが存在します。
それが「一般NISA」と「つみたて(積立)NISA」です。
名前に「NISA」という単語が共通していることから、両者が同一のものであると誤解されがちですが、実際にはその内容は異なります。
共通点は、どちらも投資から得られる収益を非課税にできるということ。
それぞれの特徴として、一般NISAは、年間120万円までの投資が可能で、投資対象商品が豊富にあります。
一方、つみたて(積立)NISAは、年間40万円までの投資となりますが、毎月一定額を長期間積み立てることを前提とした制度です。
つまり、一般NISAは、一時的な大きな利益を目指すことが可能である一方、つみたてNISAは長期間にわたり安定的に資産を増やすことを目指します。
より大きな利益を追求するか、それとも安定した資産形成を望むかで、どちらのNISAを選択するか決まります。また、一般NISAとつみたて(積立)NISAでは、非課税条件がまったく違ってきます。
これらの違いを踏まえて、あなたの投資目的に合わせたNISAを選びましょう。
非課税投資期間
| 一般NISA | つみたて(積立)NISA | |
|---|---|---|
| 非課税投資期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
つみたて(積立)NISAの非課税期間は、投資を開始した年を含めて最長20年間です。
一方、一般NISAの非課税期間は5年間ですが、これにはロールオーバーという特例が存在していました。
【ワンポイント】ロールオーバーとは
非課税期間が終了したときに、保有している投資商品を、翌年の非課税投資枠へ移すことができる制度。
これを利用すると、一般NISAは最長で10年間、非課税で運用することが可能でした。
2024年から始まる新NISAで、2023年12月31日までに購入した投資商品は5年間の非課税期間の満了に伴い、自動的に「特定口座」か「一般口座」へ払い出されます。
現行NISAで投資商品を保有している人は、非課税期間の満了時に、投資商品を清算するのか課税口座に移動するのか考えておきましょう。
参考:金融庁 令和5(2023)年度税制改正について(PDF)
非課税投資枠
| 一般NISA | つみたて(積立)NISA | |
|---|---|---|
| 非課税投資枠 | 年間上限120万円 (5年間で計600万円) | 年間上限40万円 (20年間で計800万円) |
一般NISAの年間の非課税投資枠は最大120万円まで。
対して、つみたて(積立)NISAの非課税投資枠は、年間40万円までとなっています。
この点からもわかる通り、つみたて(積立)NISAの年間非課税投資枠は、一般NISAに比べて少ないです。つまり、1年間で投資可能な金額には制限があります。
これがあなたの投資額や戦略にどのように影響を及ぼすかを理解し、それに応じて最適な選択を行うことが重要です。
一般NISAの場合、5年間で最大600万円までに。一方、つみたてNISAは20年間で最大800万円までとなります。
投資戦略によっては、短期的な運用を目指す人には一般NISAが、長期間コツコツと積立を行いたい人にはつみたて(積立)NISAが適しています。
一度に大きな金額を投資したい人や短期で利益を得たい人には一般NISAが、長期的な視野で積み立てたい人にはつみたて(積立)NISAがおすすめです。
投資方法
| 一般NISA | つみたて(積立)NISA | |
|---|---|---|
| 投資方法 | ・積立方式 ・スポット購入 | 積立方式 |
つみたて(積立)NISAと一般NISAの間には、投資の仕方にも大きな違いがあります。
つみたて(積立)NISAでは「積立方式」、一方の一般NISAでは「スポット購入」も可能です。
積立方式とは、一定の額を定期的に投資する方法です。この方法のメリットは、投資のタイミングを気にすることなく、価格が低い時には多く、価格が高い時には少ない口数を自動的に購入できます。
一方、スポット購入とは、投資家自身の判断と任意のタイミングで一括購入する方法です。
市場の動向を見て、「今が買い時だ!」と判断したときに、大量の口数を購入できます。これにより、正確なタイミングを捉えることができれば、より大きな利益を得る可能性があります。
ただし、スポット購入は市場の動向を予測し、適切なタイミングを見極めるスキルが必要となってくるでしょう。
初心者には積立方式が、市場経験と知識を持つ投資家には、スポット購入が向いているといえます。
投資対象商品
| 一般NISA | つみたて(積立)NISA | |
|---|---|---|
| 投資対象商品 | 個別株式 ・投資信託 ・ETFなど | 金融庁に届け出された投資信託233本 (2023年6月23日時点) |
つみたて(積立)NISAと一般NISAの違いの1つは、投資できる商品の種類と数です。
つみたて(積立)NISAでは、金融庁が選定した233本(2023年6月23日現在)の投資信託のみを選べます。これらの商品は、手数料が低く、長期運用に適した特徴を持つ投資商品が選ばれています。
一方、一般NISAでは、投資できる商品の自由度がはるかに高いです。
投資信託から国内外の上場株式・国内外のETF(上場投資信託)など、多様な投資商品を選べます。
つまり、つみたて(積立)NISAは、投資対象にこだわりがなく、長期的・安定的に積み立てを行いたい人向け。
一般NISAは幅広い選択肢の中から、自分で投資対象を決めたい人向け。そう分類することができます。
一般NISAのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| ①年間で非課税枠の120万円まで運用できる ②積立方式またはスポットどちらでも購入できる ③投資信託や上場株など幅広い銘柄商品を購入ができる | ①非課税の期間がわずか5年と短い ①運用資金が少額だと制度の恩恵が活かせない |
続いてNISAのメリットとデメリットについて見ていきます。まずは一般NISAから…。
一般NISAの最大のメリットは、その年間投資枠の大きさです。
最大120万円まで非課税で運用できるというのは、投資にまとまった資金を使いたい人にとっては非常に魅力的な特徴でしょう。
これを月に換算すると、毎月最大10万円まで投資できる計算になります。
一見するとメリットだらけに見えますが、不利な面についてもしっかり目を通して理解しておきましょう。
メリット① 年間で非課税枠の120万円まで運用できる
一般NISAの非課税枠は、年間120万円までとなっており、これはつみたて(積立)NISAの年間40万円と比較すると、3倍の金額を年間に投資活用できる点が大きなメリットです。
この非課税枠の違いは、大きな元手を投資に使う投資家にとっては、重要なポイントになってきます。
なぜなら、投資に使える元手が多ければ、運用益も大きくなる可能性があるからです。
運用益が非課税となるというのがNISAの特徴のため、十分な資金がある人にとっては、非課税投資枠が広いほどメリットになります。
メリット② 投資信託や上場株など幅広い銘柄商品を購入ができる
一般NISAでは、多種多様な投資商品から選ぶことが可能です。
たとえば、「国内外の上場株式」や「国内外のETF(上場投資信託)」、「投資信託」や「国内外のREIT(不動産投資信託)」など。
これにより、投資家自身の投資スタイルやリスク許容度に基づいて、自由に投資商品を選んで投資することができます。
■投資スタイルごとの商品・銘柄選択イメージ
◎できるだけリスクを取りたくない、大儲けしなくていいから安定した利益を出し続けたい
⇒ 安定した配当が見込める「投資信託」をチョイス!
◎ ある程度のリスクは許容するから、とにかく大きなリターンを目指したい
⇒ 大きなリターンが見込める成長株に投資!
したがって、一般NISAは、投資家自身の投資目的やリスク許容度に合わせた商品選択が可能であり、その自由度の高さが魅力です。
メリット③ 積立方式またはスポットどちらでも購入できる
一般NISAでは、投資商品の購入方法として、2つの選択肢があります。
それが「積立方式」と「スポット購入」です。
「積立方式」
定期的に毎月、一定の金額を投資する方法です。
これは、長期間コツコツと資産を増やしていくスタイルで、市場の値動きに煩わされることなく、堅実に投資をおこなえます。
「スポット購入」
一度に好きなタイミングで、まとまった金額を投資する方法です。
この方法は、複利の効果が働くため、うまくタイミングが合えば、一度に大きな利益を手に入れるチャンスもあります。
つまり、一般NISAは、定期的な投資でじっくり資産を増やす方法と、チャンスをつかんで一気に利益を狙う方法の、どちらも選択できるのが魅力です。
デメリット① 非課税の期間がわずか5年と短い
一般NISAの主なデメリットの1つは、非課税期間が5年と短いことです。
たとえば、2023年に開始した一般NISAの非課税期間は2027年までとなります。この期間が終了すると、その投資資産を売却するか、課税口座に移管するかの選択を迫られます。
このため、一般NISAを開始する際は、非課税期間終了後の対策もあらかじめ考慮しておくことが重要です。
ただし、いままでは期間終了後の選択肢の1つとして、「ロールオーバー」という手段がありました。「ロールオーバー」とは、非課税期間終了後、その資産を翌年の非課税枠に移行する方法を指します。
適用することで、非課税期間を再度5年間延長し、最大10年間にわたり非課税運用を継続することが可能でした。
しかし、2024年に新NISA制度ができるため、「ロールオーバー」の適用はもう使えなくなります。
自動的に新NISAの口座へ移行され、5年間の非課税期間が終了すれば、投資資産を売却するか、課税口座に移管するかの選択を迫られます。
ただし、「ロールオーバー」はできなくなりますが、資産を売却して新NISAで購入し直せば、非課税運用を続けられます。
デメリット② 運用資金が少額だと制度の恩恵が活かせない
一般NISAのもう1つのデメリット、それは非課税投資枠の最大利用が難しいことです。
一般NISAの年間非課税投資枠は120万円です。この制度のメリットを最大限に享受するためには、年間非課税投資枠をすべて利用することが理想的ですよね。
しかし、毎年30万円や50万円といった金額しか投資できない場合、年間120万円投資できる人と比較すると、非課税制度の恩恵を十分に享受できない可能性が高くなります。
さらに、年間40万円程度の投資額となると、つみたて(積立)NISAと大差ない結果になり、非課税期間の短さがデメリットに…。
つまり、一般NISAは非課税期間が短いため、可能な限り大きな投資額で利用することが理想的と言えます。
つみたて(積立)NISAのメリット・デメリット
次はつみたて(積立)NISAのメリットとデメリットです。
| メリット | デメリット |
| ①非課税の期間が最長で20年もある ②運用は少額資金から始められる ③金融知識がなくても運用商品が選べる | ①年間40万円以上は運用できない ②長期間の運用向きのため短期には向いていない |
つみたて(積立)NISAの主要なメリットは、非課税期間が最長20年という長期間に及ぶこと。一般NISAの5年と比較しても長く、長期的な資産形成を目指す方にとっては大きな魅力です。
また、つみたて(積立)NISAの年間非課税投資枠は40万円で、一般NISAの120万円と比較すると少額です。
これは一見するとデメリットのように思えますが、逆に言えば、少ない金額からでも投資を始められるというメリットにもなります。
また、つみたて(積立)NISAでは、投資できる商品が限定されている点も特筆すべき点です。
これは投資初心者にとっては非常にありがたい制度で、複雑な投資選択をせずに、投資を始めることができます。
メリット① 運用は少額資金から始められる
つみたて(積立)NISAは、投資初心者であっても、財布の紐が固い方でも、この制度を通じて手軽に投資を始められます。
最低投資額が非常に低く、一部の商品では100円の元手から始められてしまいます。これにより投資を、いつでも始められる身近な存在として認識できるでしょう。
メリット② 非課税の期間が最長で20年もある
つみたて(積立)NISAの強みは、長期間の非課税運用能力です。
最長20年間も非課税運用が可能であり、選択できる投資商品は、長期投資に適しています。
長期にわたり資産を増やすことを目指す投資家にとって、つみたて(積立)NISAは理想的な制度といえます。
たとえば、2023年につみたて(積立)NISAで投資を開始すれば、その投資は2042年まで、非課税のまま運用することもできます。
メリット③ 金融知識がなくても運用商品が選べる
つみたて(積立)NISAは、投資初心者でも安心して投資ができる制度です。
なぜなら、どの商品に投資すれば良いか迷ってしまう初心者に対して、金融庁が定めた基準をクリアした200本以上の投資信託を用意しているからです。
これらの投資信託は、長期投資に適しているとされており、初心者でも安心して選択できるように設計されています。
投資商品は、金融庁の定めた基準をクリアした長期投資に適している商品であるため、短期的な利益を追求するよりも、中長期の運用に向いていることを覚えておきましょう。
デメリット① 年間40万円以上は運用できない
つみたて(積立)NISAは、気軽に始められる投資方法とされていますが、その投資可能枠は年間40万円までと決まっており、それ以上の金額を投資することはできません。
また、投資商品の購入方法が積立方式を採用しているため、投資可能枠を月計算に直すと、[40万円÷12か月=毎月約33,333円]以内までの投資となります。
たとえば、500万円の資金があり、すべてを投資に活用したいと考えている人にとっては、つみたて(積立)NISAの制限はデメリットとなるでしょう。なぜなら、つみたて(積立)NISAでは、全額を一度に投資することはできないためです。
大きな金額をまとめて投資したいと考えている人は、他の投資手段を模索した方が良いでしょう。
デメリット② 長期間の運用向きのため短期には向いていない
つみたて(積立)NISAは、その特性上、短期間の売買(デイトレーディング)には不向きです。
その理由は2つあります。
1つ目の理由
つみたて(積立)NISAが、長期的な資産形成を目的とした制度であること。
そのため、短期間での価格の上下に注目するよりも、長い時間をかけて資産価格が徐々に上昇する可能性がある投資商品に注目するのが主な運用方法です。
2つ目の理由
一度売却した場合に、その年の非課税枠が再度戻らないというルールがあること。
つみたて(積立)NISAで投資を始めたら、基本的にその資産は、長期保有することが最善策です。
これらの理由から、短期的な売買を頻繁にする投資家には、つみたて(積立)NISAは向いていません。
【一般NISAがおすすめな人】大きな資金があり自分の考えで投資をしたい人
一般NISAは、資産運用を楽しみながら手元資金を増やしたいと考えている方には、ぴったりの投資手段です。
特に、次の2つの条件を満たす人なら一般NISAを検討する価値は大いにあるでしょう。
- 大きな資金が手元にある
- 自分の考えで投資を行いたい
なぜ一般NISAがこれらの条件を満たす人に適しているかは、非課税投資枠の大きさと、投資の自由度の高さにあります。
一つずつ見ていきましょう。
おすすめな人① ある程度まとまった大きな資金がある人
一般NISAの特徴として、年間最大120万円までの投資が非課税となる点が挙げられます。
1年間に120万円を丸々投資に充てることが可能なら、一般NISAの恩恵を最大限受けられるわけです。
また、一般NISAは、月々の積立方式に限らず、まとまった金額を一度に投資することも可能です。
一般NISAが投資信託や株式投資などの商品を、自由に選べる点と合わせて、手元にある大きな資金を、よりスピーディに資産形成したいと考える方にとっては、大きな利点となります。
おすすめな人② 金融知識があり自分で考えて投資をしたい人
一般NISAは、投資信託から個別の上場株式まで、投資先の選択肢が豊富であるため、自分で商品を吟味し、投資を楽しみたいという人に向いています。
さらに一般NISAでは、スポット購入が可能です。
【ワンポイント】スポット購入とは
好きなタイミングで好きな金額で購入すること。たとえば、株価の下落時に一括で投資する手法など。
スポット購入は、投資の醍醐味を味わいたい方にとっては大きなメリットと言えます。
また、投資を通じて「会社の株主になりたい」という方にも、一般NISAはおすすめの投資方法といえるでしょう。
【つみたて(積立)NISAがおすすめな人】少額から始めて長期で運用したい人
一般NISAはある程度の資金を持っている人向きでしたが、つみたて(積立)NISAに向いているのはどんなタイプの人になるでしょうか?
真っ先に挙げられるのは次の2つのタイプでしょう。
おすすめな人① 毎月1〜3万円を投資に使いたい人
つみたて(積立)NISAは非課税投資枠が年間40万円で、月換算すると、毎月約33,333円までの投資制限をされており、投資を始めるための障壁を低くしています。
また、金融機関によっては、最低投資金額がわずか100円〜のところも。
無駄遣いしているお金や、お小遣いの一部を、毎月投資に充てるという使い方も可能です。
つみたて(積立)NISAは、投資を気軽に始めたい方や、まずは少額から始めたいと考えている方にとって、おすすめの投資制度です。
おすすめな人② 老後資金を心配している人
つみたて(積立)NISAでは、投資を開始した年から約20年間、あなたの投資は非課税状態で運用されます。たとえば、2023年に始めた場合、20年後の2042年末までは、運用益の税金を気にすることなく成長できます。
長期運用を前提にしているため、日々の値動きを細かくチェックしたり、毎日の市場の動きに一喜一憂する必要がないという点も、投資初心者や忙しい人にとっては大きな魅力です。
つつみたて(積立)NISAは、20年後の老後資金を考えている方や、毎日の市場動向を追いかけるのは疲れるから、できる限り放っておいて運用したいという方にもおすすめです。
投資初心者はどちらのNISAを選ぶべき?
それぞれのNISAに向いている人のタイプを解説しましたが、一般NISAとつみたて(積立)NISAどちらの制度を選ぶべきかを考える際、投資家の現状や考え方などで、その適性が明確に異なります。
一般NISAは次のような人におすすめです。
- 短期間で、まとまった大きな金額を投資したい人
- 個別の株式に投資したい人
- 自分で売買のタイミングを判断して投資できる人
つみたて(積立)NISAは次のような人におすすめです。
- 少額で長期間積み立てをしたい人
- はじめて投資を始める人
- 金融庁が認めた投資商品で安定運用したい人
投資が初めての人にとっては、少額から始められ、商品選びも簡単な、つみたて(積立)NISAの方がやりやすいと思われます。
投資初心者でも、一般NISAを使い投資で資産形成は可能ですが、投資商品の選択肢の多さや、投資のタイミングに悩む可能性があります。
その点つみたて(積立)NISAであれば少額資金から始められ、自動的に積立がおこわれ、長期にわたって安定した運用が期待できるため、初めての投資でも安心して始められます。
【年代別比較】一般NISAとつみたて(積立)NISAのどちらがお得?
ここからは、一般NISAとつみたて(積立)NISAの状況を詳しく見ていきます。
金融庁の発表では、2022年12月末時点で「一般NISA」と「つみたてNISA」の口座総数は、1,804万4,165口座あります。
| NISA総口座数 | 1,804万4,165口座 |
| 一般NISA | 1,079万0,929口座 |
| つみたて(積立)NISA | 725万3,236口座 |
この表から分かることは、「一般NISA」の口座数が多いことです。
一般NISAの口座が多いということは、金融知識がある投資家もしくは、まとまった大きな金額を持っている投資家が、いち早く非課税制度に目を付け、一般NISA口座を開設したと読み取れます。
| 年代別比率 | 一般NISA | つみたてNISA | ||
| 総数 | 1064万5891口座 | 100% | 638万5158口座 | 100% |
| 20代 | 40万5266口座 | 3.8% | 125万3195口座 | 19.6% |
| 30代 | 106万3284口座 | 10.0% | 183万9965口座 | 28.8% |
| 40代 | 158万8324口座 | 14.9% | 158万4079口座 | 24.8% |
| 50代 | 190万9973口座 | 17.9% | 107万3409口座 | 16.8% |
| 60代 | 222万8046口座 | 20.9% | 46万0122口座 | 7.2% |
| 70代 | 227万0139口座 | 21.3% | 15万0277口座 | 2.4% |
| 80代 | 118万0859口座 | 11.1% | 2万4111口座 | 0.4% |
次に、年代別の、一般NISAとつみたて(積立)NISAの口座数割合を見てみます。
ここで読み取れることは、一般NISAは50代以降の口座数が多く、まとまった大きなお金を持っている層の口座数が多いということです。
反対に、つみたて(積立)NISAでは、20代から30代の口座数が多く、つみたて(積立)NISAの恩恵が最大限受けられる、長期での運用を考えている方が多いようです。
一般NISAとつみたて(積立)NISA、各年代ではどちらを活用した方がお得なのでしょうか? 20、30、40、50代ごとに比べてみました。
【20代の場合】つみたて(積立)NISAがおすすめ
20代の方には、つみたて(積立)NISAをおすすめします。
つみたて(積立)NISAの非課税期間は長く、20年間です。
投資においては、長い期間をかけるほど「複利」の効果が大きくなるため、20年間をフルに利用すれば、大きな資産を築ける可能性が高まります。
【ワンポイント】複利とは
「配当に配当がつく」状態のこと。投資の初期段階では元本にしか配当はつきませんが、配当を再投資することにより、配当に配当が付くようになり、運用益がだんだん大きくなる効果があります。
十分な期間を確保できる20代の方には、この複利効果を最大限に利用できる、つみたて(積立)NISAが適していると言えるのです。
20代は、一般的に収入がまだ少なく、貯金も少ない人が多いため、消費する前に資産形成への割り振りをおこなうことで、無理なく資産形成ができるでしょう。
長期的に資金を増やすことができれば、結婚や出産後も教育資金として利用できます。
また、将来的には本格的な投資を行いたいと考えている場合、20代のうちに一般NISAを利用して投資について学ぶこともおすすめです。
【30代の場合】つみたて(積立)NISAがおすすめ
30代から投資を始めるのであれば、つみたて(積立)NISAをおすすめします。
30代になると、仕事での昇進による収入増が見込め、また結婚や出産などのライフイベントに対しての生活設計に対して真剣に考える時期です。
子供の教育資金や親の介護費用・自身の老後資金問題など、さまざまな目的に対する資金計画が必要になってくることでしょう。
つみたて(積立)NISAは最長20年の運用ができるため、早い時期から資産運用を始めれば、資金を堅実に増やせる可能性が高くなります。
当面の間、大きな資金を必要としないのであれば、つみたて(積立)NISAを選ぶ方がメリットがあるかもしれません。
【40代の場合】つみたて(積立)NISAがおすすめ
40代の方には、つみたて(積立)NISAがおすすめです。
40代は、教育資金や医療費、親の介護費用や老後の資金問題など、お金の悩みが尽きません。
そのため、まとまった大きな金額を短期で資産を運用するのではなく、毎月の積立投資で将来の資産を築ける、つみたて(積立)NISAが堅実な選択となるのではないでしょうか。
つみたて(積立)NISAは、積立金額が柔軟に設定でき、教育費や医療費、介護費用などの予想外の出費にも対応できます。
また、積立設定に従って自動で取引が行われるため、忙しい中での投資も容易です。
投資初心者や投資商品にこだわりがない方にも、つみたて(積立)NISAは適しています。なぜなら、投資初心者が迷う投資商品選びでは、金融庁の基準を満たすリスクの少ない投資商品から選べるからです。
つみたて(積立)NISAは、その柔軟性と自動化されたシステムにより、40代のライフスタイルにもピッタリ当てはまります。
なお、ある程度のまとまった大きなお金があり、投資経験のある人であれば、短期でも資産形成ができる一般NISAをおすすめします。
【50代の場合】つみたて(積立)NISAがおすすめ
結論から言うと、50代から始める投資もつみたて(積立)NISAがおすすめです。
50代は年収が頂点に近づく一方で、大きな支出が落ち着くことから、資金が貯まりやすい時期といわれています。また、定年を視野に入れた年代であり、年金生活に入ることを意識しはじめる頃でもあります。
つみたて(積立)NISAは、最長で20年間利用することができるため、毎月少額ずつでも、積み立てるように貯蓄を増やすことが可能です。
投資商品選びでは、金融庁による厳しい審査をクリアした、投資信託やETFなどの投資商品であるため、投資初心者でも安心して購入できます。
そのため、50代から投資を始めても、大きなリスクにはなりません。
まずは、これから必要となる老後資金や親の介護費用などを見据え、つみたて(積立)NISAで、確実に資産を増やすことを目指してはいかがでしょうか。
なお、投資経験が豊富で、ある程度まとまった資金がある場合は、一般NISAを選ぶのもありでしょう。
一般NISA・つみたて(積立)NISAの併用はできないが切り替えは可能
一般NISAを選択したものの、実際に運用を始めてから「やっぱりつみたてNISAが良かったかも…」と、後悔してしまうことがないか、心配性の方なら気になってしまうと思います。
でもご安心ください。一般NISAとつみたて(積立)NISAは併用できませんが、口座を移行することは可能です。
ただし、移行するタイミングと非課税枠については注意が必要なので、しっかり覚えておきましょう。
移行するタイミング
すでにその年に一度でもNISA口座で取引をしたならば、その年には口座を移行できません。
しかし、9月までに移行手続きを申し込み、12月までに手続きを終えれば、次の年からは新しい口座での投資を開始できます。
非課税投資枠
一度利用した非課税枠は、再度使うことはできません。
したがって、一般NISAからつみたて(積立)NISAへの口座移行をする場合は、一般NISAの非課税枠120万円を使い切った上で、翌年からのつみたて(積立)NISAへの切り替えを申し込むと良いでしょう。
一般NISAとつみたて(積立)NISA間で、直接的に保有商品の移行はできませんが、切り替えた後も同じ口座で非課税期間いっぱいまで保有し続けられます。
移行後にすぐに売却するか、課税口座に移すかも選択肢の1つですが、非課税期間を最大限に利用するためにも、期間が終わるまでは保有し続け、その後に行動を決めることがおすすめです。
一般NISAとつみたて(積立)NISAの併用が2024年の新制度により可能になる
2024年、NISAは新しい制度に変わります。
現在のNISA制度には、一般NISAとつみたて(積立)NISAという2つの枠組みがあります。
一般NISA
年間上限投資額が120万円で、非課税保有期間が5年間。
つみたて(積立)NISA
年間上限投資額が40万円で、非課税保有期間が20年間。
現在のNISA制度では、NISA口座は併用ができないため、一般NISAとつみたて(積立)NISAのどちらかの制度を選択する必要がありました。
しかし、2024年から始まる新しいNISA制度では、両方を併用できるようになります。
これにより、投資戦略に幅が出て、より投資家の目標に合わせて賢く運用することができます。
【比較】おすすめネット証券会社5選
あなたがNISAで投資を始めたいならば、投資商品を購入するために、まずは金融機関で口座を開設する必要があります。
金融機関には銀行と証券会社がありますが、ネット証券会社がお手軽でおすすめです。
ネット証券会社では、NISA制度に力を入れており、投資が初めての方でも安心して取引ができるように、サポート体制も充実しています。
投資商品の豊富さや手数料の安さなどで、ネット証券会社の口座数は年々増加傾向にあります。
さらに、投資をするだけでポイントが付与されそのポイントで投資商品を購入できるなど、お得なサービスがあり、このサービスを上手く使えばお金を使わずに資産が増えていくでしょう。
ネット証券会社は数多くあるため、ここでは代表的な会社の特徴を表にまとめました。
いずれも、投資初心者がはじめて口座を開設するような会社です。それぞれの特徴を比較して、検討してみてください。
| 口座開設数 | つみたてNISA 取扱銘柄数 | 投資信託本数 | 最低積立金額 | ポイント付与 | ポイント投資 | 口座開設時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 公式サイト | 1,000万口座超え※1 | 197銘柄 | 2,688本 | 100円~ | TポイントPontaポイントdポイントVポイント(クレカ積立) | 可能 Tポイント Pontaポイント Vポイント | 最短で翌営業日 |
 公式サイト | 900万 口座超え | 192銘柄 | 2,634本 | 100円~ | 楽天ポイント | 可能 | 最短で翌営業日 |
 公式サイト | 145万 口座超え | 173銘柄 | 1,692本 | 100円~ | 投資信託の月間平均保有額に応じて松井証券ポイントが貯まる (ただし、保有銘柄等の指定あり) | 可能 (ただし松井証券が厳選した3種類の投資信託のみ) | 最短で翌営業日 |
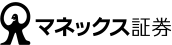 公式サイト | 222万 口座超え | 168銘柄 | 1,360本 | 100円~ | マネックスポイント | 可能 | 最短で翌営業日 |
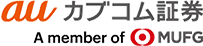 公式サイト | 156万口座超 | 192銘柄 | 1,643本 | 100円~ | Pontaポイント | 可能 (投資信託およびプチ株の買付) | 最短で翌営業日 |
※1 SBI証券、SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOの合算
SBI証券

| 口座開設数 | 1,000万口座超え ※SBI証券、SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOの合算 |
| つみたて(積立)NISA 取扱銘柄数 | 197銘柄 |
| 投資信託本数 | 2,688本 |
| 最低積立金額 | 100円~ |
| ポイント付与 (投資信託保有時) | Tポイント Pontaポイント dポイント Vポイント(クレカ積立時のみ) |
| ポイント投資 | 可能(Tポイント/Pontaポイント/Vポイント) |
| 口座申込から 開設・取引までの日数 | 最短で翌営業日 |
SBI証券のおすすめポイント
- 多くの投資家から高い評価を得ている
- ポイントサービスがある
- ポイントで投資商品の購入ができる
SBI証券は、初心者から経験豊富な投資家まで幅広く利用されているネット証券会社です。その信頼性と品質は、1,000万口座突破という業界内での記録によって証明されています。
また、SBI証券では、さまざまなポイントサービスを提供しています。たとえば、投資信託の積立にクレジットカードを利用している際や、保有している投資信託の残高に応じて、ポイントの獲得が可能です。
このポイントは、TポイントやPontaポイント・dポイントなど、あなたの好きなポイントを選び利用できます。
さらに、SBI証券では、投資信託の購入に「Tポイント」が使えます。1ポイント1円相当換算して、最低1ポイントからの利用ができ、利用上限もありません。
このため、投資で獲得したポイントを、さらに投資に活用できるメリットがあります。
楽天証券

| 口座開設数 | 900万口座超え |
| つみたて(積立)NISA 取扱銘柄数 | 192銘柄 |
| 投資信託本数 | 2,634本 |
| 最低積立金額 | 100円~ |
| ポイント付与 | 楽天ポイント |
| ポイント投資 | 可能 |
| 口座申込から 開設・取引までの日数 | 最短で翌営業日 |
楽天証券のおすすめポイント
- 月3万円以上投資すると、楽天市場のポイント還元率が0.5%上がる
- 楽天カードで積立決済を行うと、最大で1%のポイント還元がある
- 貯まったポイントで、投資信託の購入に利用できる
楽天証券は、楽天グループの利用者には、特におすすめのネット証券会社です。
楽天証券と楽天銀行を連携させて、投資信託に月3万円以上投資すると、楽天市場のポイント還元率が0.5%上がる特典があります。
また、楽天証券は、楽天カードを利用して積立決済を行うと、最大1%のポイントが還元され、保有する投資信託の残高が一定金額に達すると、その分もポイントが還元されます。
さらに積み立てたポイントは、投資信託の購入に利用することも可能です。つまり、投資活動を通じてポイントを得て、そのポイントを再投資に使うという良い循環が生まれます。
松井証券

| 口座開設数 | 145万口座超え |
| つみたて(積立)NISA 取扱銘柄数 | 173本 |
| 投資信託本数 | 1,692本 |
| 最低積立金額 | 100円~ |
| ポイント付与 | 投資信託の月間平均保有額に応じて松井証券ポイントが貯まる (ただし、保有銘柄等の指定あり) |
| ポイント投資 | 可能 (ただし松井証券が厳選した3種類の投資信託のみ) |
| 口座申込から 開設・取引までの日数 | 最短で翌営業日 |
松井証券のおすすめポイント
- 信託報酬の一部を、毎月現金またはポイントとして還元
- サポート体制が充実している
- 顧客ファーストを実現
松井証券は、手数料の還元や高品質なサポート体制、利便性の追求を通じて、投資家に利益をもたらす証券会社です。
最大の特徴の1つは、投資信託の信託報酬の一部を、投資家に還元する独自のシステム。松井証券が受け取る信託報酬の0.3%を超える部分を、現金またはポイントで投資家に還元しています。
このため、投資家は最大0.85%の信託報酬をポイント還元分として受け取れます。
サポート体制も評判で、「問い合わせ窓口格付け(証券業界)」で、12年連続三つ星を受賞。
また、顧客の利便性を重視し、投資への参入障壁をさげるため、投資家の銀行口座から証券口座への引落手数料や、他社からの乗り換え手数料も松井証券が負担しています。
マネックス証券

| 口座開設数 | 222万口座超え |
| つみたて(積立)NISA 取扱銘柄数 | 168銘柄 |
| 投資信託本数 | 1,360本 |
| 最低積立金額 | 100円~ |
| ポイント付与 | マネックスポイント |
| ポイント投資 | 可能 |
| 口座申込から 開設・取引までの日数 | 最短で翌営業日 |
マネックス証券のおすすめポイント
- 投資信託の保有残高に応じてマネックスポイントが獲得できる
- 米国株および中国株への投資に強い
- NISA口座を利用してのIPO投資ができる
マネックス証券は、投資と日常生活の利便性を両立させたい方におすすめのネット証券会社。
マネックスカードを使用することで、投資信託の保有残高に応じてポイントを獲得できます。これらのポイントはAmazonギフトカードやPontaポイントなどに交換できます。
さらに、積立投資にマネックスカードを使用すると1.1%のポイントが還元されます。
米国株と中国株に広く対応しており、5,000銘柄以上の米国株と多くの中国株を扱っており、これらの成長市場への投資を検討している投資家にとっては大きな魅力です。
さらに、NISA口座を通じてIPO投資を行うことができます。
IPOに当選すれば大きな利益を得るチャンスがあり、その利益はNISA口座を通じてあれば非課税となります。
auカブコム証券

| 口座開設数 | 156万口座超え |
| つみたて(積立)NISA 取扱銘柄数 | 192銘柄 |
| 投資信託本数 | 1,643本 |
| 最低積立金額 | 100円~ |
| ポイント付与 | Pontaポイント |
| ポイント投資 | 可能(投資信託およびプチ株の買付) |
| 口座申込から 開設・取引までの日数 | 最短で翌営業日 |
auカブコム証券のおすすめポイント
- 1株からの購入が可能な「プチ株」
- 人気の自社開発ツールがある
- au PAYカードで積立額を決済するとPontaポイントが貯まる
auカブコム証券は、少額投資から始めたい初心者から経験豊かな投資家まで、幅広いニーズに対応することが可能なネット証券会社です。
1株からの購入が可能な「プチ株」はNISA口座でも取り扱いがあり、非課税枠を満額使わずとも、少ない資金で株式取引を始められます。
電話相談や株主優待情報の提供といった、細やかなサービスが評価されていますし、投資家のさまざまなニーズに対応した、自社開発ツールの提供も魅力的。
au PAYカードを利用して毎月の積立額を決済すると、カード決済額に対して1%のPontaポイントが貯まります。貯まったポイントは、投資信託の購入や「プチ株」のサービスに利用でき、また、全国190万か所以上の店舗やサービスでも使用できます。
一般NISAとつみたて(積立)NISAおすすめ銘柄商品5選
ここからは、一般NISAとつみたて(積立)NISAにおすすめの銘柄商品を5つ紹介します。銘柄選びの参考にお役立てください。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| ファンド設定日 | 2018年10月31日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 連動対象 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) |
| 運用区分 | インデックス型 |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 0.1133% |
| 純資産総額 | 1,212,615百万円 |
| リターン(1年) | +10.43% |
| 販売会社 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・マネックス証券 ・松井証券 など他24社 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の特徴
- 投資リスクを軽減できる
- 運用のコストが低い
- 複利で資産が増えやすい
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、賢く運用益を増やしたい方に、ピッタリのインデックスファンド。あなたのお金が、アメリカだけでなく、ヨーロッパやアジアなど、世界中の株式市場で活動します。
市場の動きに合わせて自動で国や銘柄を調整するため、特定の国や地域に縛られず、安定した成長を目指せるのがポイントです。
また、このファンドは、業界内でも屈指の低コストを誇ります。
運用のコストが低いということは、投資のリターンが減らされることなく、しっかりと手元に戻ってくるということです。さらに、分配金はファンド内で再投資ができるため、複利の力で税金の心配をせずに、じっくりと資産を増やせます。
これは、長期的な資産形成を考えると、かなり大きな強みです。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
| ファンド設定日 | 2017年2月27日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 連動対象 | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
| 運用区分 | インデックス型 |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 0.09889% |
| 純資産総額 | 494,974百万円 |
| リターン(1年) | +11.43% |
| 販売会社 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・マネックス証券 ・松井証券 など他23社 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの特徴
- 先進国の大型・中型企業の株式を広くカバー
- 運用コストが低い
- 分散投資でリスクを軽減
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、日本以外の先進国にまとめて投資ができるファンド。先進国株式指数をベンチマークとしており、主に先進国の大型・中型企業の株式を広くカバーしています。
このファンドは「eMAXIS Slim」シリーズの1つで、この商品の特徴として「運用コスト(信託報酬)が非常に低い」ことが挙げられます。
運用コストは、長期投資においては、最終的な収益に大きな影響を及ぼすため、コストが低いことは投資家にとって大きなメリットです。
なお、株式から得られた配当はファンド内で再投資されるため、分配金はでません。このため、この投資商品を使えば効率良く資産形成ができます。
さらに、多数の企業の株式に投資しているため、単一銘柄への投資リスクを軽減するとともに、国や地域・業種にわたる広範な分散投資ができます。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
| ファンド設定日 | 2017年5月9日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 連動対象 | 国内外の株式・債券・リートの8資産 |
| 運用区分 | バランス型インデックス |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 0.143% |
| 純資産総額 | 205,991百万円 |
| リターン(1年) | +4.05% |
| 販売会社 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・マネックス証券 ・松井証券 など他22社 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の特徴
- 幅広く分散投資ができる
- 運用コストが低い
- 投資金額は100円から
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、国内外の8つの資産に投資することで、あなたの資産をしっかりとバランス良く成長させることを可能にします。
1つの投資信託で世界の株式や公社債・不動産投信など、多種多様な資産に投資することで、特定のリスクに左右されずに安定的な資産形成を目指せます。
年間の信託報酬は、わずか0.143%。同じ8つの資産に投資する他の投信と比べても、はるかにお手頃です。
さらに、この投信はNISA口座でも購入ができるため、非課税のメリットをフル活用しながら、運用益を賢く増やせます。
しかも、投資金額はたったの100円からで、投資初心者や少額から始めたい方にも手が出しやすいでしょう。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
| ファンド設定日 | 2017年9月29日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 連動対象 | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |
| 運用区分 | インデックス型 |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 0.162 % |
| 純資産総額 | 991,746百万円 |
| リターン(1年) | +10.66% |
| 販売会社 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・マネックス証券 ・松井証券 など他16社 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンドの特徴
- 世界中の多くの国と地域の株式に投資でリスクを分散
- 運用コストが低い
- 投資初心者でも手軽に国際分散投資を始めることができる
楽天・全世界株式インデックス・ファンドは、世界の株式市場に広く分散投資をおこないながら、低コストで資産の運用をすることを目的としたインデックスファンドです。
このファンドは、世界中の多くの国と地域の株式に投資し、1つの国や地域に依存せず、広範な分散投資ができるためリスク分散が可能です。
インデックスファンドは、アクティブファンドに比べて、ベンチマークに連動する運用成果を目指す手法であるため、運用コストが低くなる傾向にあります。
また、容易に投資商品の購入と売却ができるため、投資初心者でも手軽に国際分散投資を始めることができます。
iFree 8資産バランス
| ファンド設定日 | 2016年9月8日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 連動対象 | 投資成果を特定の指数の動きに連動 |
| 運用区分 | バランス型 |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 0.242% |
| 純資産総額 | 57,200百万円 |
| リターン(1年) | +4.22% |
| 販売会社 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・マネックス証券 ・松井証券 など他62社 |
iFree 8資産バランスの特徴
- 多様な資産への分散投資
- 8つの異なる資産に分散投資をしてリスクを軽減している
- 定期的に自動的で資産の再配分をおこなう
iFree 8資産バランスは、8つの異なる資産に分散投資できる投資商品の1つで、リスクを軽減しながら安定収益を目指す投資信託です。
海外への投資割合が6、国内への投資割合が4の配分となっており、海外商品を中心にバランス型の投資をしたい投資家には魅力的な投資商品といえるでしょう。
国内外の株式や国内外の債券・コモディティなど、8つの異なる資産に分散投資をしているため、特定のアセットクラスや地域にリスクが集中することを避け、リスクを分散できます。
このファンドは、定期的に自動的で資産の再配分をおこない、各資産のウェイトを均等に保つことで、一定のリスクやリターンを維持します。これにより投資家は手動での調整をすることなく、バランスの良いポートフォリオを維持することが可能に。
また、最低投資額が低く設定されているため、初心者や少額から投資を始めたい方でも手軽に始められます。
一般NISA・つみたて(積立)NISAの違いに関するよくある質問
ここでは、一般NISAとつみたて(積立)NISAの違いに関する、よくある疑問や質問に回答します。
一般NISA・つみたて(積立)NISA口座を開設した後に他の金融機関に変更できる?
NISA口座は1年ごとに金融機関を変更できます。
金融機関の変更は、変更を希望する年の前年の10月1日から、変更を希望する年の9月30日までに手続きを行う必要があります。
ただし、変更したい年の1月1日以降に変更前の金融機関で、NISA口座で投資商品の購入をした場合、その年は金融機関の変更はできません。
一般NISA・つみたて(積立)NISA口座は複数の金融機関で開設はできる?
NISA口座は、1人につき1口座しか申し込み・開設ができません。
つまり、複数の金融機関で口座を開設することはできません。
2023年度のNISA非課税枠を使うにはいつまでに銘柄の買付けをすればよいですか?
NISA制度を利用する際、「受渡日」と「約定日」の理解が必要です。
| ◎受渡日とは |
| 投資信託の売買注文が成立した後、実際に売買代金が支払われる日のことを指します。 |
| ◎約定日とは |
| 注文が成立した日を指します。 |
NISA制度を年内で使い切るためには、「受渡日」が年内になるように計画することが必要です。このため、何営業日後が「受渡日」になるかを逆算し、注文手続きを行う必要があります。
たとえば年内に投資枠を使い切るには、積立設定で投資商品の買付日を毎月30日に設定していると、「約定日」が12月27日、「受渡日」が翌月の月4日となる可能性があります。
非課税枠が翌年扱いになることを防ぐために、日数の余裕を持って買い付けをしましょう。
さらに、投資している商品によっては「受渡日」が異なるケースがあるため、投資する商品の詳細を事前に確認しておくことも重要です。
たとえば、国内株式の場合、「受渡日」は「約定日」から起算して3営業日目となります。
一般NISA・つみたて(積立)NISAはiDeCoと併用はできる?
一般NISAとiDeCoまたは、つみたて(積立)NISAとiDeCoは、同時に利用できます。
しかし、一般NISAとつみたて(積立)NISAは、並行して利用できません。
資金に余裕がある場合は、iDeCoと一般NISAまたは、つみたて(積立)NISAとの併用を検討することで、より効果的な投資と節税を達成できます。
これらの制度を上手に活用することで、賢くお金を運用し、将来の生活資金や老後資金を増やすことが可能です。
【まとめ】一般NISA・つみたて(積立)NISAの違いまとめ
この記事のポイント
- 一般NISAとつみたて(積立)NISAの共通点は「非課税である」ことだけ
- 非課税投資期間、非課税投資枠、投資方法に違いがある
- 少額から始めて超長期(10年以上)で運用したいなら「つみたて(積立)NISA」
- 投資経験者で、まとまった大きな資金を活かすなら「一般NISA」
- 20代からNISAを始めれば、最大限の恩恵が受けられる
一般NISAとつみたて(積立)NISAは、非課税であるという点を除いては、まったく違います。
この記事を参考に違いを理解して、自分にあったNISAを選んでみてください。
もしも、決断するのが難しいのなら…、大きい資金を活かすことを考えているなら一般NISAを、少額から長期間運用したいならつみたて(積立)NISAを検討してみてはいかがでしょうか。